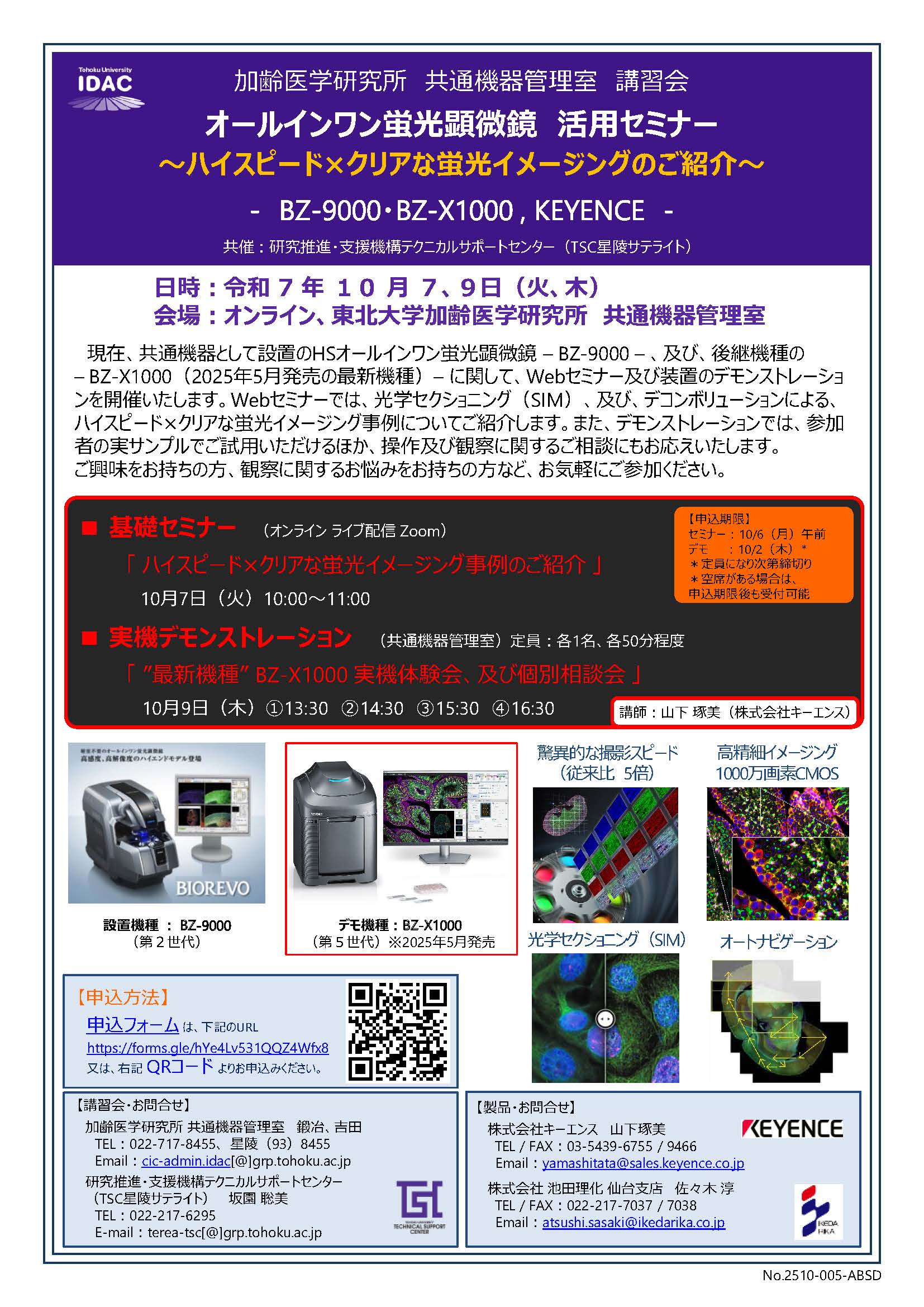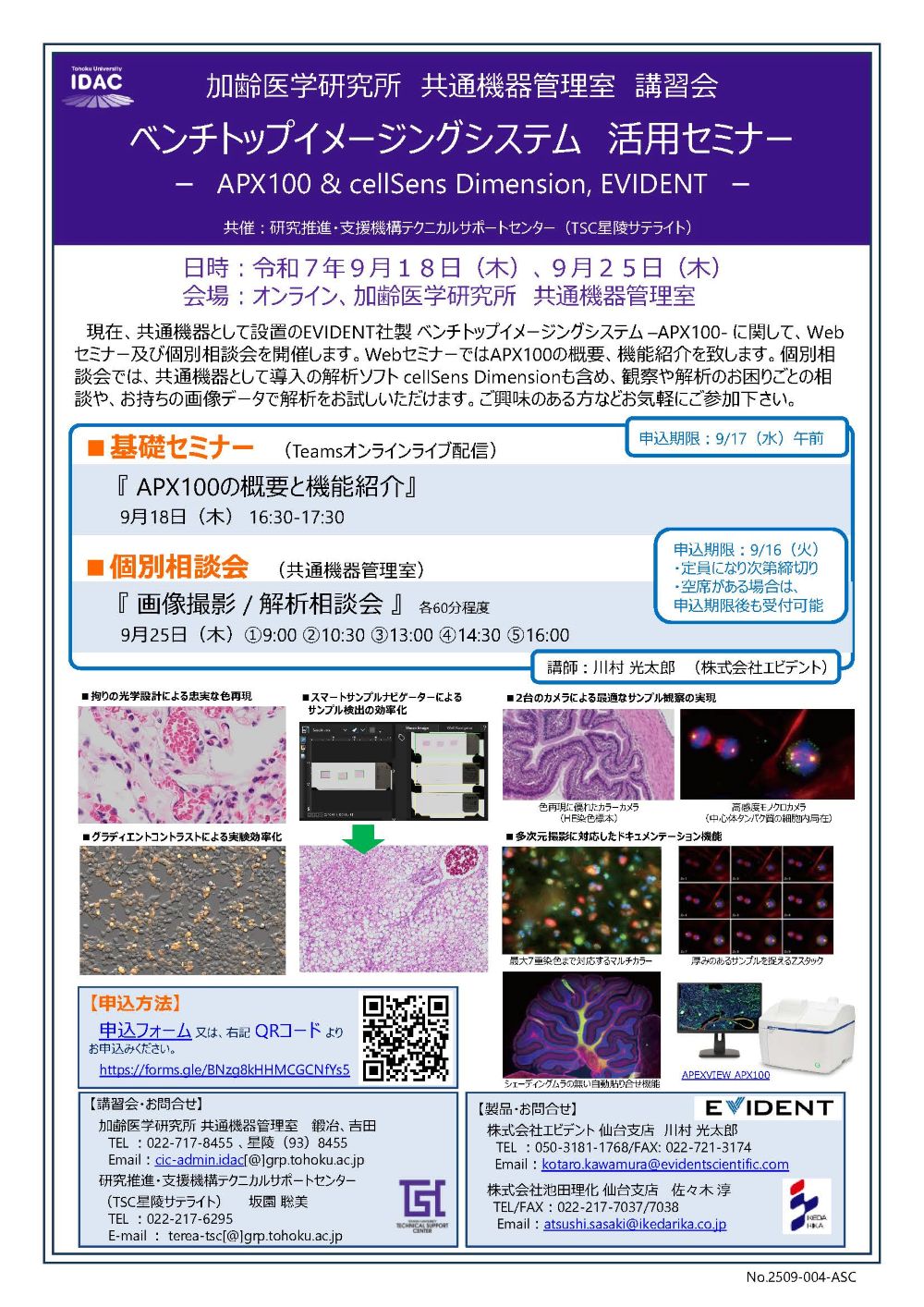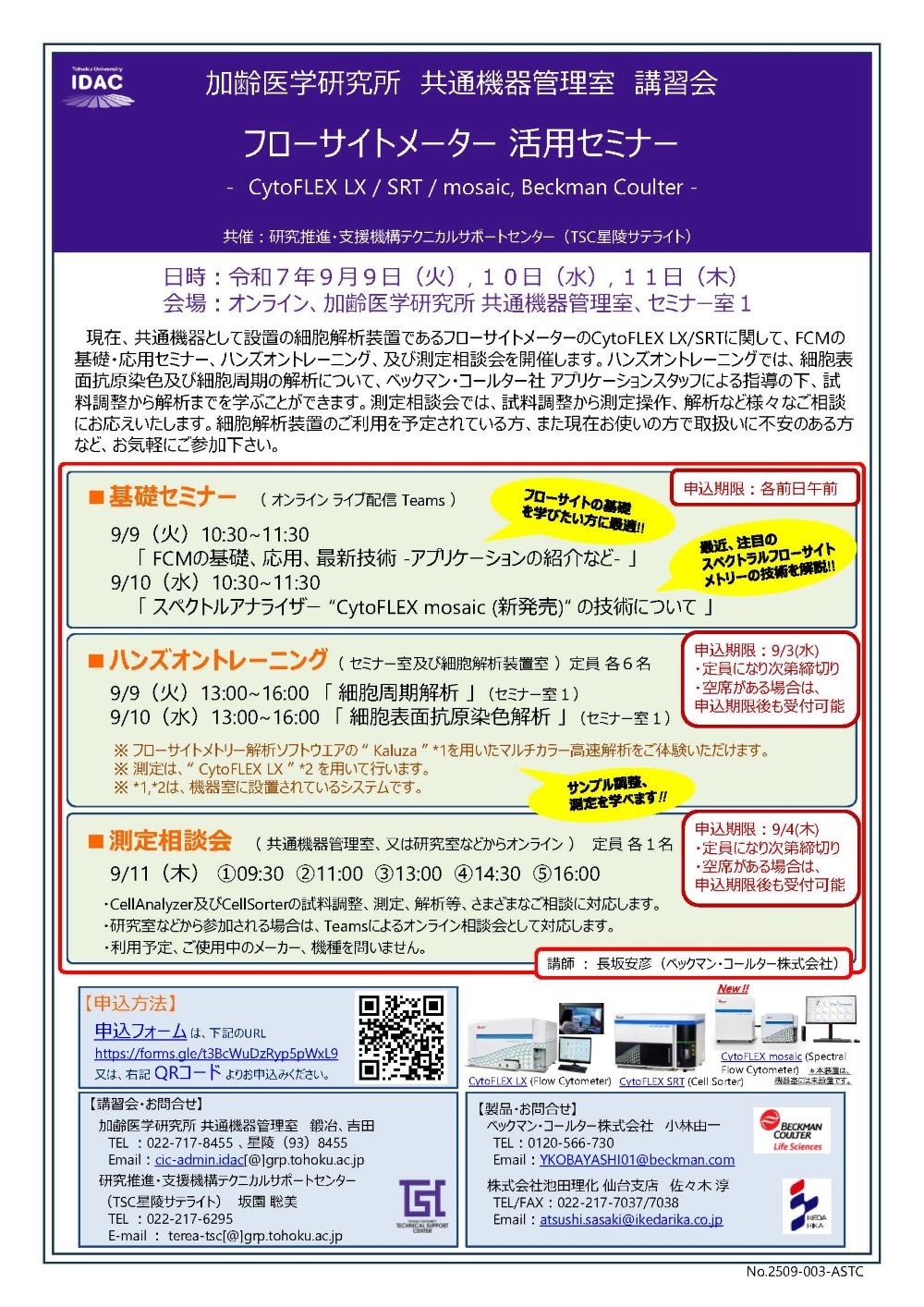◇ 2025年9月25日(木)加齢研セミナーのご案内
| 日時: | 2025年9月25日(木) |
| 場所: | 加齢医学研究所 スマート・エイジング研究棟4階 セミナー室 |
| 演題: | 高齢社会のための実践に基づく・参加型ITデザイン |
| 講師: | Müller, Claudia先生 |
| 所属: | ジーゲン大学 第III学部 高齢社会のためのIT |
| 要旨: | The research group of Prof. Dr. Claudia Müller (Faculty III, “IT for the Ageing Society,” University of Siegen) conducts research and teaching at the intersection of demographic change and digital transformation. Its central focus is the practice-based and participatory design of socio-technical infrastructures and digital solutions in the field of “health & ageing.” The goal is to maintain and expand social participation of older and vulnerable people, enhance their mobility and independence, and support wellbeing, health, and quality of life at home. In particular, through the living-lab approach called “Praxlabs,” the team collaborates with diverse stakeholders such as older adults, caregivers, family members, and service providers. Within this framework, researchers explore everyday practices in real-life contexts, co-design innovative IT artifacts, and study the processes of their appropriation and transformation. Furthermore, to introduce non-tech-savvy participants step by step to new technologies, the group applies co-creation methods based on social and experiential learning, fostering the development of skills, competences, and positive attitudes. This lecture will present these practice-based and participatory IT design approaches and discuss their significance for ageing societies. |
| 担当: | 瀧 靖之(臨床加齢医学研究分野・内線8559) |
| 連絡先: | オガワ 淑水(臨床加齢医学研究分野・内線8492) |