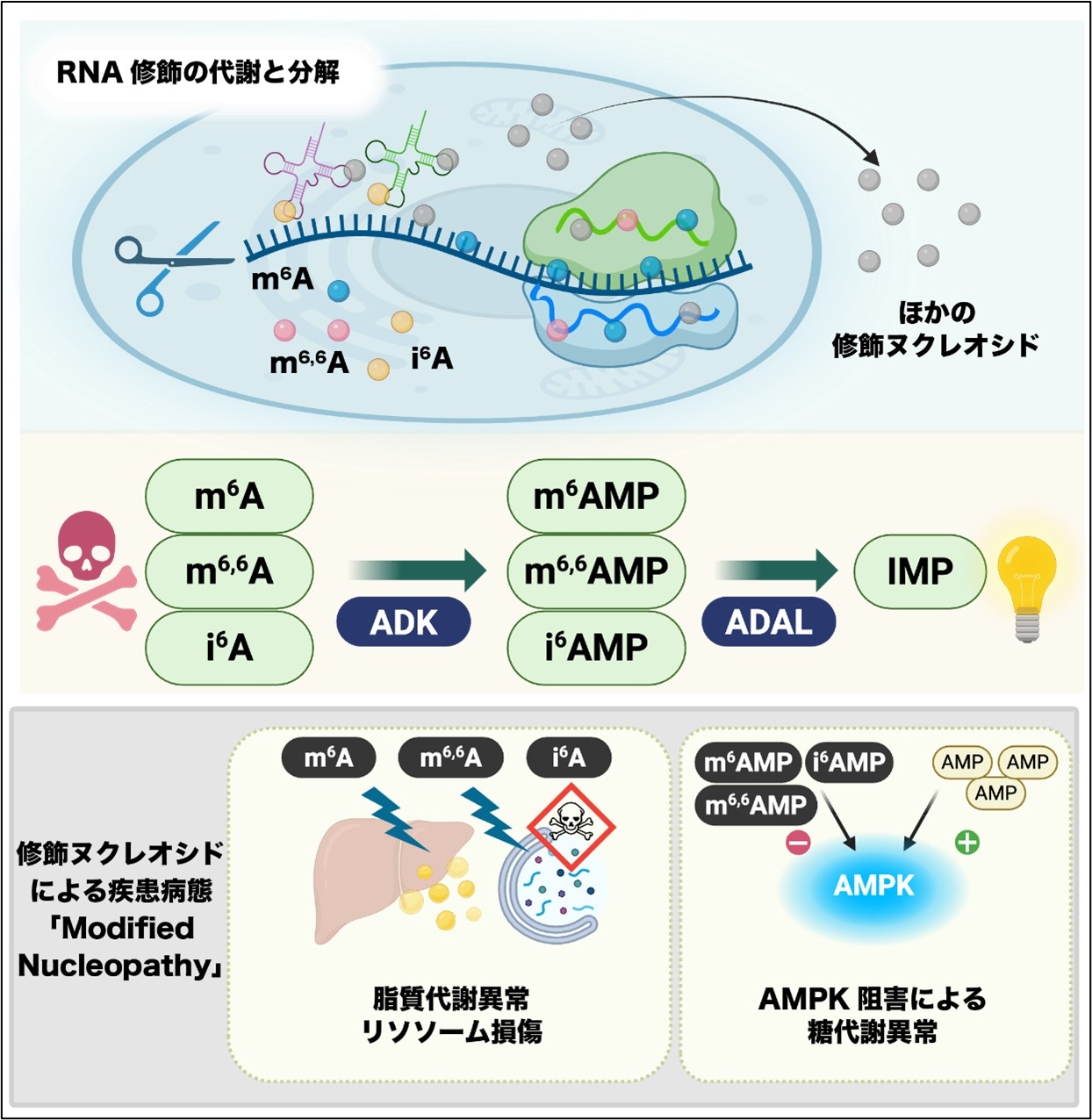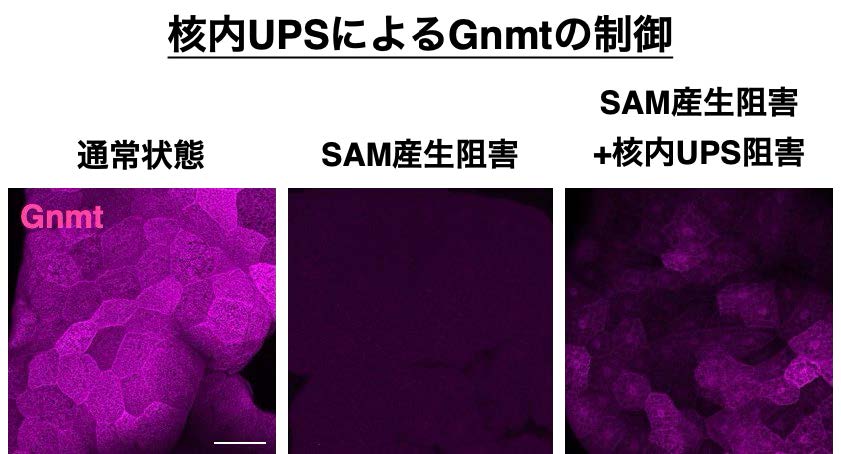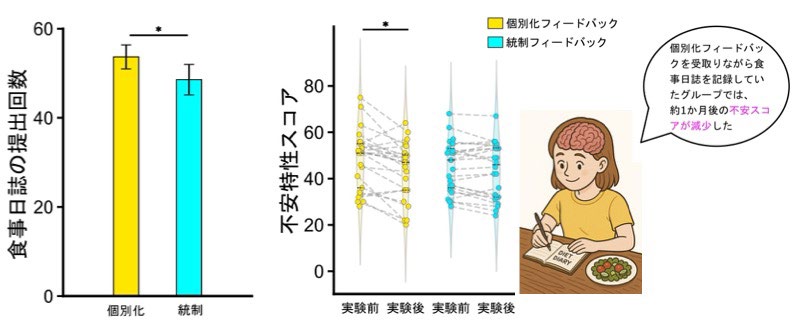【概要】
理化学研究所(理研)開拓研究所岩崎RNAシステム生化学研究室の岩崎信太郎主任研究員、脇川大誠リサーチアソシエイト、水戸麻理テクニカルスタッフⅠ、山城はるな特別研究員(研究当時)、戸室幸太郎大学院生リサーチ・アソシエイト、七野悠一上級研究員(研究当時、現筑波大学医学医療系教授)、東京大学大学院理学系研究科の濡木理教授、伊藤弓弦准教授、安藤佑真大学院生、同大学大学院工学系研究科の鈴木勉教授、長尾翌手可講師、東北大学加齢医学研究所の魏范研教授、谷春菜助教、熊本大学大学院生命科学研究部の富澤一仁教授、中條岳志准教授らの共同研究グループは、ミトコンドリア[1]内で行われるタンパク質合成(翻訳[2])の動態(ダイナミクス)を高精度に観測する新しい手法を開発し、ミトコンドリア翻訳[3]の複雑な動態、疾患での制御不全などを明らかにしました。
本研究成果は、ヒトのエネルギー代謝を担うミトコンドリアの仕組みの理解や、ミトコンドリア病[4]などミトコンドリア翻訳異常に関わる疾患の理解につながるものと期待されます。
ヒトの細胞の中には細胞質で起こる翻訳以外にもミトコンドリアの内部で起こる翻訳が存在します。ミトコンドリア内の翻訳を網羅的かつ高解像度に多検体で解析する手法は、望まれつつもこれまで存在しませんでした。
今回、共同研究グループは、新たに「MitoIP-Thor-Ribo-Seq法[5]」という手法を開発し、ミトコンドリア翻訳速度の計測や、ミトコンドリアtRNA(mt-tRNA)[6]修飾による翻訳の促進効果、ミトコンドリア病患者の細胞での翻訳制御不全といった、複雑な翻訳動態を明らかにしました。
本研究は、科学雑誌『Molecular Cell』オンライン版(11月12日付:日本時間11月13日)に掲載されました。

MitoIP-Thor-Ribo-Seq法によるミトコンドリア翻訳のダイナミクスと複雑性の解明

図1. Ribo-Seq法とその課題
(A)Ribo-Seq法の概要。RNase処理:mRNAを分解する酵素で処理すること。オープンリーディングフレーム:mRNAの開始コドン(塩基3個の配列)から終止コドンまでの塩基配列。
(B)Ribo-Seq法によって得られるフットプリントの割合。細胞質リボソームフットプリントに比べ、ミトコンドリアリボソームフットプリントは圧倒的に少ない。
【補足説明】
[1] .ミトコンドリア
真核細胞内に存在する小器官で、独自のDNAを持ち、アデノシン三リン酸(ATP)を産生する「エネルギー工場」。
[2] .翻訳
メッセンジャーRNA(mRNA)([7]参照)に記された塩基配列をアミノ酸配列へ変換し、リボソーム([8]参照)でアミノ酸を結合してタンパク質を合成する過程。
[3] .ミトコンドリア翻訳
ミトコンドリアDNAから写しとられたmRNAからタンパク質を合成する過程。ミトコンドリア内で、専用のミトコンドリアリボソームによって行われる。
[4] .ミトコンドリア病
ミトコンドリア機能異常に基づく多臓器疾患の総称。代表的な病例として、脳卒中様エピソード(MELAS)([16]参照)、ミオクローヌスてんかん(MERRF)があり、ミトコンドリア翻訳異常が病因となることが多い。
[5] .MitoIP-Thor-Ribo-Seq法
ミトコンドリア免疫沈降法(MitoIP)とRNA増幅法(Thor([11]参照))を組み合わせることでミトコンドリアリボソームの解析に特化したRibo-Seq法([9]参照)。網羅的かつ高精度にミトコンドリア翻訳を解析できる。
[6] .ミトコンドリアtRNA(mt-tRNA)
ミトコンドリアDNAにコードされる22種類の転移RNA(tRNA)の総称。ミトコンドリアリボソームにmRNA情報に基づいたアミノ酸を供給し、翻訳伸長([14]参照)を支える。
【問い合わせ先】
(研究に関すること)
東北大学加齢医学研究所
モドミクス医学分野 教授 魏 范研
助教 谷 春菜
TEL: 022-717-8562
Email: fanyan.wei.d3*tohoku.ac.jp, akiko.ogawa.e5*tohoku.ac.jp
(*を@に置き換えてください)
(報道に関すること)
東北大学加齢医学研究所
広報情報室
TEL: 022-717-8443
Email: ida-pr-office*grp.tohoku.ac.jp
(*を@に置き換えてください)