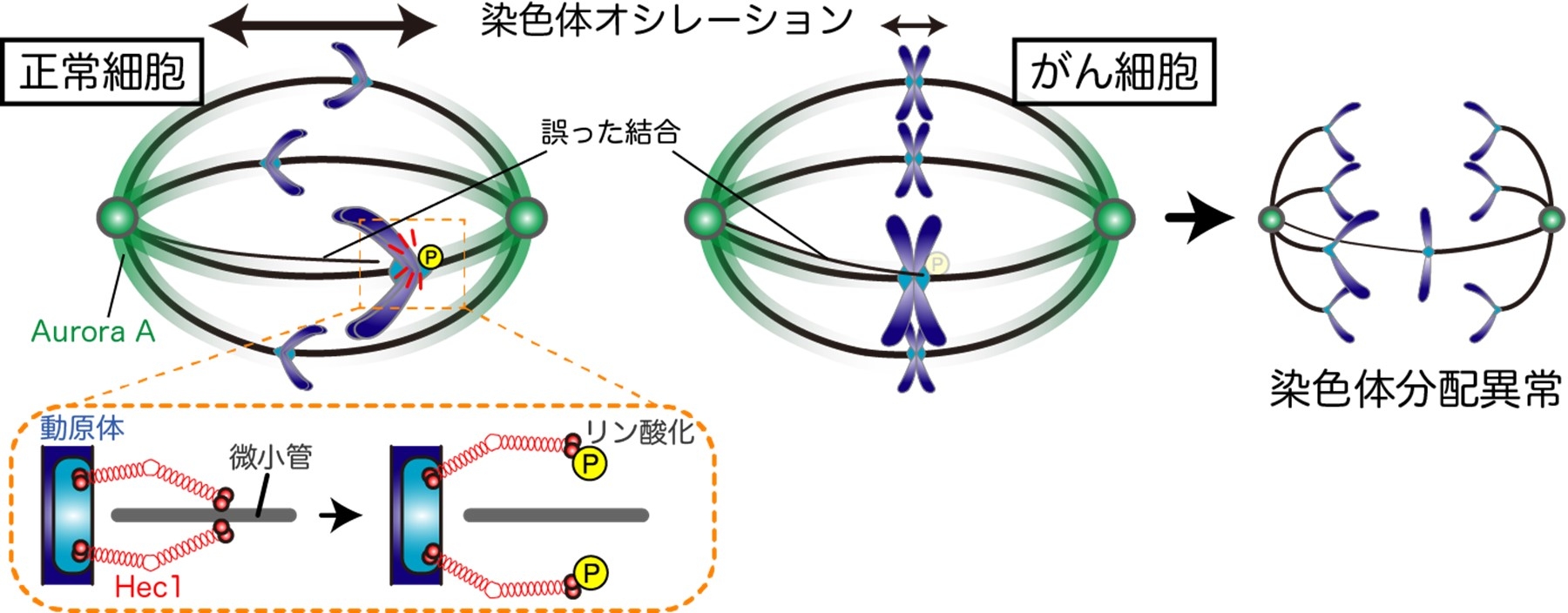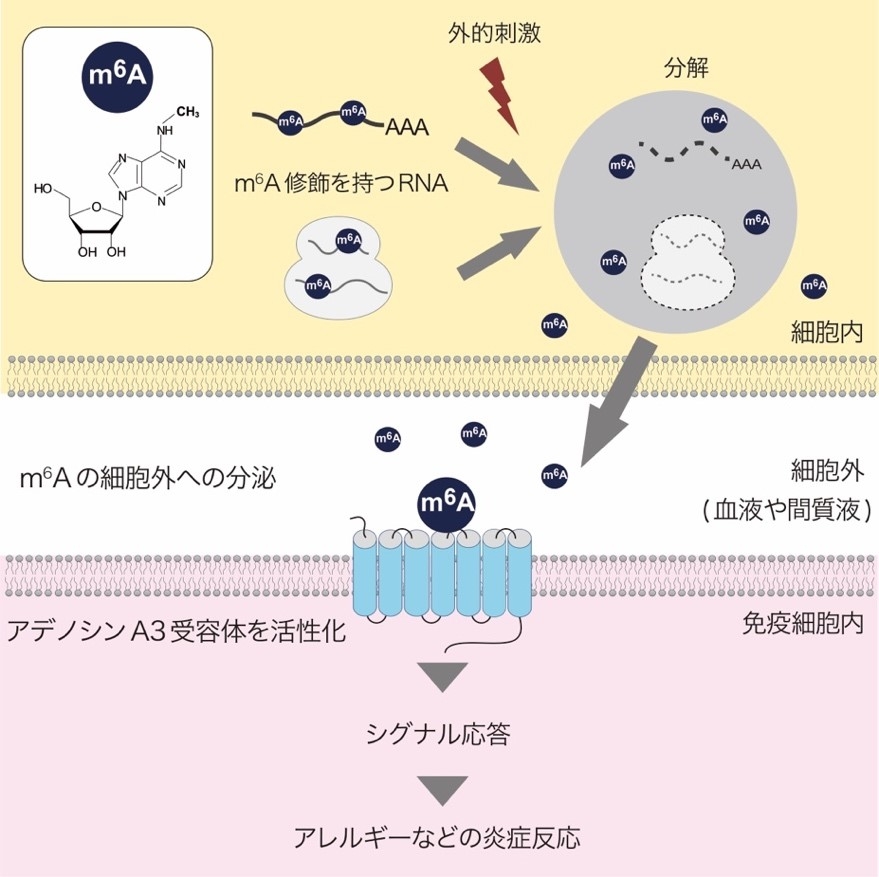【オンライン開催】加齢医学研究所研究員会主催 荒井啓行教授退職記念講演 IDAC Seminar to commemorate the retirement of Professor Arai
日時:
令和3年3月9日(火)16時~17時
Tuesday, 9 March 2021, 16:00~17:00
オンライン開催(Zoom)
講 師:荒井啓行 Hiroyuki Arai
所 属:東北大学加齢医学研究所 脳科学研究部門 老年医学分野
Department of Geriatrics & Gerontology, Division of Brain
Science, Institute of Development, Aging and Cancer, Tohoku University
演 題:アルツハイマー病の理解と克服に向けた脳科学研究
For better understanding of Alzheimer’s disease and development
of disease-modifying therapy
連絡先:冨田尚希(所属 老年医学分野 ・内線 7182 )
Naoki Tomita (Department of Geriatrics & Gerontology, ext7182)
要 旨: アルツハイマー病(AD)の症状改善薬として、塩酸ドネペジルなど4種類の薬剤が保険収載され、日常診療に広く用いられている。一方で、アミロイド蛋白の生成阻止、除去或いは凝集阻害などADの発症メカニズムに介入し、病勢を停止させることが期待される「疾患修飾薬」は、最も重要かつ切望されている薬剤であり、一刻も早く優れた治療薬が実用化されることが望まれ、臨床現場において大きな「Unmet
Needs」となっている。2025年までに疾患修飾薬を市場化する目標に向けて、2020年現在アミロイド抗体薬など121種類の新薬治験が進行中である。特に、認知症と呼ばれる進行したステージのADではなく、発症前AD,
前駆期ADなど(超)早期段階における疾患修飾薬治験が主流となりつつある。また、治験を支援するツールとして高精度バイオマーカーの開発が必須とされ、脳脊髄液タウ・リン酸化タウ、Aβ42、アミロイドイメージング、タウイメージングは概ね標準化され、治験遂行の重要なツールとなっている。現在さらに、脳病理像を反映した簡便な血液バイオマーカーの開発が精力的に進められている。