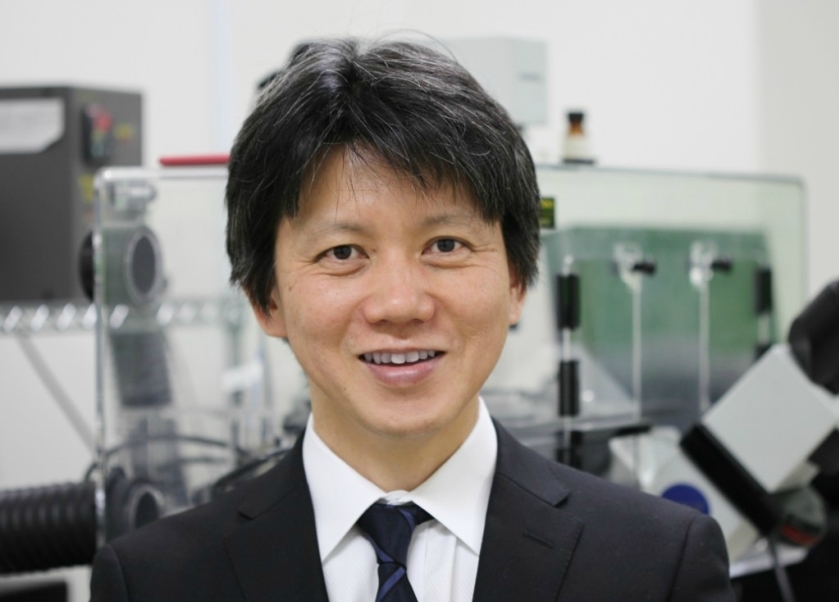

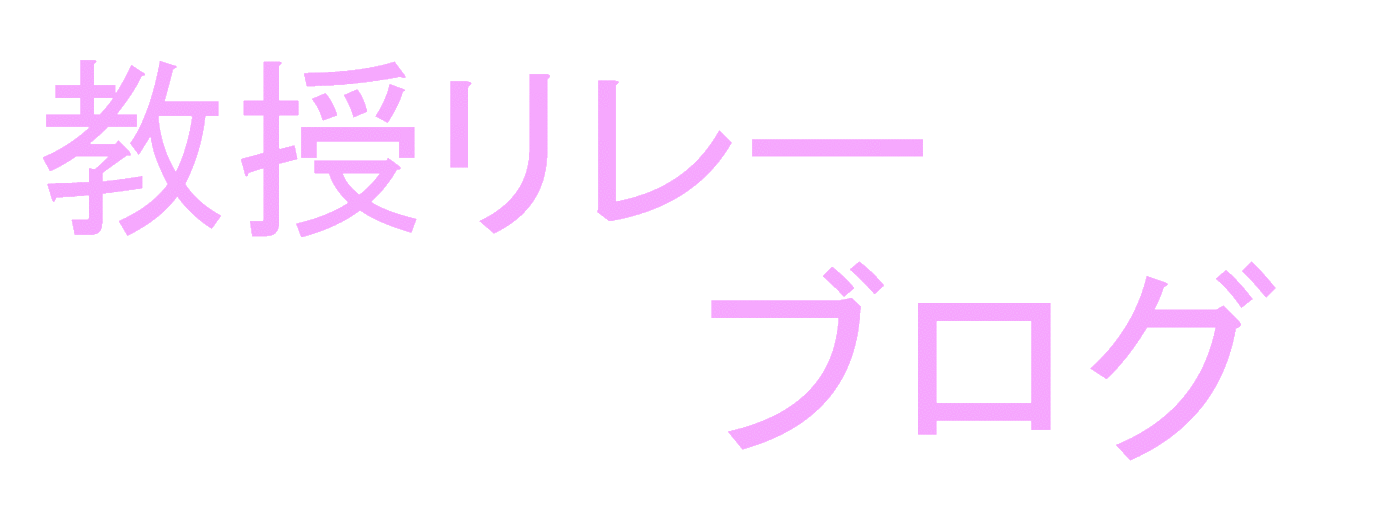
田中 耕三
Kozo TANAKA
内なる肖像
F. ジャコブ自伝
内なる肖像
F. ジャコブ自伝
昨年春、新型コロナウィルスの感染拡大により、会議や講義はオンライン(これは今も変わらない)、学会も中止、学生は自宅待機、ただ時間だけはあるという時期があった。その時ふと、オペロン説でノーベル賞を受賞したF. ジャコブの自伝「内なる肖像−一生物学者のオデュッセイア」(みすず書房, 1989年)を手に取った。これは2011年の大震災で実験ができない時に、20代を第二次世界大戦に従軍して過ごしたジャコブの境遇に通じるものを感じて入手したものだ。しかし、あまりにも文学的な書き出しに途中で挫折してしまっていたのだが、今回また同じような状況になって、あらためて読み進めてみた。
読んでわかったのだが、戦争で研究が中断されたわけではなく、そもそも研究を始めたのが戦後30歳になってからであり、全体の3分の2は生い立ちや戦争中のエピソードに費やされている。しかし、研究とは全く関係のないその頃のエピソードの一つ一つが、その後につながるジャコブの「内なる肖像」を作り上げており、予定調和的な伝記よりも共感を覚えた。パスツール研究所でルウオフ、モノと研究を始めてからの残り3分の1についても、ノーベル賞に繋がる着想とその後の研究の進展が語られるのは最後の30ページであり、受賞の5年前、ノーベル賞につながる論文を投稿した1960年で物語は終わっている。
学生の頃、時系列的な理解なしに初めてオペロン説を聞いた時には、当たり前のような気がしてピンと来なかった。これは本書で言うところの「科学というものは、いったん認められ、教材になってしまうと、冷たいものである」ということであり、本人の口から生き生きと語られるその経緯は、熱気と興奮にあふれている。そもそも遺伝の本体がDNAかタンパク質かが議論されていた頃から、1953年にDNAの構造が解かれるのと並行して研究を進め、遺伝子の実体もよくわかっていない中でセントラルドグマの核心となる転写の概念に至る過程はスリリングだった。前半の叙情的で文学的な語り口もさることながら、「目的に向かって直進し、少なくとも手はじめとしては、細部にはかかずらわらない」、「仮説の大胆さに躊躇しない」といった洞察に富んだ文章に、発見につながる姿勢のようなものを感じ、この困難な状況の中でも研究する喜びを再認識させられた。
次回は、腫瘍生物学分野の千葉先生です。
名 前:田中 耕三(たなか こうぞう)
出身地:鹿児島県
趣 味:犬の散歩
分野名:分子腫瘍学研究分野
出身地:鹿児島県
趣 味:犬の散歩
分野名:分子腫瘍学研究分野
